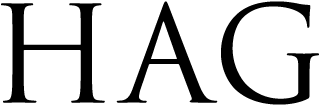家にまつわる記憶や思い出、住まいや暮らしへの想いなどを、さまざまな人の自由な視点で語らうコラム『家の記憶と、』。 第6回目の語り手は、長崎市出島にある〈List:〉の店主・松井知子さん。住まいとお店、共に築60年を超えるコンクリート造りのビルで生活する松井さんは、ふたつのビルが重ねてきた時間や記憶について語ってくれました。暮らしにまつわるショップやギャラリーを営み、なんでもない一日一日を自分らしく過ごす松井さんだからこそ、家を見つめるまなざしは、そこで暮らし、生きてきた人々の物語へ。自身が生まれ育った家や、月日を重ねたビルから感じる“気配”から、単なる無機質な箱ではない、記憶の詰まった“家”というものの存在に思いを馳せます。
「家の記憶」
最初にこのタイトルを聞いた時、私は家が記憶しているものについてと、主語を取り間違えた。家が人間のように記憶を持つわけはない。でも私がそう思ってしまったのには理由がある。それは私の仕事場のあるビルと、自宅の部屋の建物が共に築60年を超えていて、それぞれ町の中で独特の佇まいをしているからだ。高度成長期にコンクリートで造られたふたつのビルは、まるでその土地で年輪を重ねていく樹木のごとく、そのビルに住まう人たちと共に、静かに記憶を重ねているようだ。毎日ふたつのビルの古い階段を上り下りして10年を超えた。私の記憶も刷り込まれているのだろうか。


まずは子供の頃の私の記憶から。私が子供の頃に暮らした家は、父の仕事場の2階にあった。まるで時計代わりのように、正午きっかりに父が2階に上がってお昼ご飯を食べ、仕事終わりの父と一緒に、兄や妹と順番にお風呂に入った後、家族揃って晩ご飯を食べる、そんな規則正しい生活を毎日繰り返していた。父や母に用事があると、いつでも従業員の人が2階のドアをノックして入って来ていたし、父は急用で夜でも仕事に出かけることも多く、業者の人たちは私たちと遊んでくれたりと、家族以外の人が自宅に居ることが日常だった。だから私にとっての子供の頃の家の記憶は、父の仕事と絡み合っていることが多い。というよりは、父の仕事場に家族と住んでいた、と言う方が感覚的に近いかもしれない。
両親と祖母、私たち4人兄弟と家族も多く、一時住み込みで働いている人もいたこともあり、大人たちはいつも台所で食事の用意をしていた。小学生の頃になると、私は何か料理の手伝いがしたくて、いつも大人たちの足元にまとわりついていた。インゲン豆の頭を折り、スジがスーッと取れた時は嬉しかったし、椅子に膝立ちしながら、大きなすり鉢の底で形がなくなっていく胡麻が、じんわりと油をにじませてくるのを眺めていた。台所のテーブルに広げたチラシの上に、餃子や春巻きがどんどん並んでいく様子は楽しくて、時折晩ご飯作りが小さなイベントになった。そういえば、今でも私は台所で誰かと一緒に料理したり、後片付けをしたりする事が好きだ。それは子どもの頃からなのかと、この原稿を書きながら気づき、その家の記憶と今の私が重なった。
家の記憶と言っても、残念ながら私のお気に入りの場所は、家の中ではない。それは父が書斎にしていた離れの隣にある庭と、洗濯物干しに使っていた3階の屋上だった。小さな庭の中央には、細く美しい枝を伸ばす木蓮の木があり、庭を囲むフェンス沿いに植えられたツツジや山吹は、春になると競うように咲き乱れ、小さな岩で囲ってつくった小さな池には、お祭りで買ってきた金魚やメダカが泳いでいた。庭に面したガラス窓の外には、半畳ぐらいの平たい岩が敷いてあった。そこは部屋の続きみたいで、私はそのゴツゴツとした岩に寝転がり、庇に作られていた藤棚を見上げるのが好きだった。細い外階段で上がる3階の屋上からは、遠くに大村湾が見渡せた。中学生になると、屋上の壁をよじ登り、外にせり出した縁のない2階のベランダの屋根の地べたに座り、伸ばした両足の先に見える、海に浮かぶ空港に向かって少しずつ下降していく飛行機を眺めた。思春期の悩みごとの多くは、湖のように穏やかな水面が光る海を眺めながら、ひとりで静かに消化していたように思う。そしてあの飛行機に乗って、軽やかにどこでも行ける大人になりたいと思っていた。
両親が家や持ち物に執着するタイプではないようだと感じたのは、県外の会社を辞めてその家に戻った時だ。高校生の頃から大村の家を出て長崎市内で暮らしていたので、私がその家に住むのは実に20年ぶりだった。家庭菜園をしていた山手の土地に、数年前に新しく平家の家を建てて暮らし始めていた両親は、必要なものだけを持って出て行った様子で、家の中はもう使うことがないもので溢れていた。台所の棚には食器類が並び、窓辺の収納には、私たち兄弟が幼稚園や小学校で描いた絵などがたくさん残されていた。自分が描いたのかすら分からない絵や、折り紙が貼られた画用紙の束を見ながら、子どもの頃の私たちも置いて行かれてしまった感覚になったのを覚えている。店を始める前とオープン後も含め、私は1年半ほどそこに暮らした。その間少しでも自分の場所に近づけたいと、会社員時代に買い揃えたお気に入りのうつわに、庭から花を摘んで生けてはみたが、父の仕事場の空気を払拭することはできなかった。

家の記憶。私が主語を間違えたのは、私が今、かつてその場所に居た人たちの気配を感じながら日々暮らしているからだと思う。時々私のギャラリーの部屋に、年配の方が懐かしそうに入ってきては、このビルの歴史を語ってくれる事がある。自宅の大家さんも、以前このビルに住んでいた家族の話や、かつてこのビルで成長していった子供たちの様子を楽しそうに話してくれた。全ての部屋の前の住人がどんな人だったかを知っているし、小さなビルなので住人は全て顔見知りで、時折すれ違う階下の子供たちの成長に驚く。廊下に響く声や足音が、大家さんとの立ち話が、私たちの暮らす音のひとつひとつが、このビルに記憶として沁み込んでいくのを感じる。時空と空間を超えたその気配に包まれながら、仕事場と自宅、それぞれのビルで私の暮らしは作られている。そしてそれは本当に居心地がよく、優しくて風通しがいい暮らしだ。そう、このふたつの部屋は、私が私らしく暮らしていると自信をもって言える。そして、いつか別の場所に移ることになっても、ここで私の暮らした気配が小さな記憶になり、まだ知らない誰かを包む気配になれるなら、私は潔くこのふたつの部屋を去るだろう。
プロフィール
松井知子
長崎県在住
List:オーナー
2006年出島にて暮らしにまつわるセレクトショップ〈List:〉をオープン。2016年にギャラリー形態に変更し、およそ月に1度、洋服や陶磁器、ガラス、家具など、個人作家やデザイナーの展示を開催している。